【石黒謙吾さんインタビュー】人と違うこと、役に立たないことこそが“粋”

期待と現実、そして恋愛トラブルの20代
石黒さんは画家志望だったとか?
小学校3年生のときの図工の女の先生が、先生とは思えないほど自由な人で、いつも「こういう絵を描いておいて」とだけ言って、図工室の隣にある控室でのんびりしているんですよ。
『絵の先生ってすごくいい仕事だな』と思った(笑)。
だから、画家になりたいというより、絵の先生になりたかったんです。
だったら美術大学に行かないといけないんだろうと思って、それ以外はあまり深くは考えていなかったんですよ。
図工の先生になりたくて東京芸大を目指すわけですね。
僕は金沢の出身なんですけど、金沢には金沢美術工芸大学があって、僕の周りにも美術家志望の人が多くて、当たり前のようにみんな金沢美大に行くもんだと思っていました。
だけど、高校生になったときに、3人組のアイドル、キャンディーズにはまって、『東京に行くしかない』と思いました。
僕が高校3年の春にキャンディーズは解散するんですけど、それでも『3人のいる東京に行こう』みたいな意識は強くて、高校を卒業したら上京しました。
そして、3浪して東京芸大は挫折するわけですよね。
いや、挫折ということもなかったですね。
そもそも、予備校である御茶の水美術学院に行って早々に、『東京芸大はムリだな』と思いました。
周りのみんなが上手くて。予備校に入ってすぐに挫折していた。
でも、そのときはショックとかはあまりなかったですね。

デッサンでも上手い人はすごく上手いですからね。
見ただけで「自分の力のなさ」がわかるんです。
予備校は半年は通って、あとは惰性で在籍していた感じです。
名曲喫茶でアルバイトして、終わったら酒飲んで、徹夜で麻雀して、昼まで寝て、という生活をまる2年。とにかくだらだらしていました。
でも、21歳のときに『これはまずいな~』とさすがに思いました。
『このままでは俺はダメになる』と考えて、それで日本ジャーナリスト専門学校に行こうと決めたんです。
絵も好きだったけれど、雑誌も好きだったんですよ。
キャンディーズのなかでも好きだった伊藤蘭さんが女優として1980年に復活していたので、『マスコミの仕事をやっていれば、会えるかもしれない』というのが最大の理由です(笑)。
女の子と付き合うという気持ちはなかったのですか?
高校生の間はずっとそうでしたね。女の子に気持ちが行かなかった。
同級生の女の子を好きになるという感覚にならないほど、ランに夢中でした。
いま考えるともったいないですね(笑)。
でも、19歳から21歳までは女の子と同棲してたんですが、その彼女に家財道具一式持っていかれて……。
えっ! どういうことですか?
名曲喫茶でバイトに入ってきた女の子と同棲し始めたんです。
そして、新小岩の2万円のアパートから中野の6万円のアパートに友人と2人で引っ越して、家財道具なんかも揃えました。
そこに、友人と入れ替わりで彼女と2人で住み始めたんです。
でも、僕は日本ジャーナリスト専門学校に行くようになって、時事通信社でバイトもはじめたから、忙しくて帰らなくなったんですね。
2か月くらいしてある日、帰ったら、家のなかが空っぽ。人生で大きい挫折は美大を諦めることよりもそのことでしたね。
ショックでしたよ。
頭が真っ白になった。
ステレオなんかがひとつもない。
卒業アルバムからなにからなにまで。卒アルはそんなにショックじゃなかったけれど、一生懸命に集めたキャンディーズグッズが……。
それは痛いですね。
特にケンカしたこともなかったのに。僕の人生であれが一番、しんどかったな。
いまでもすっきりしないままですよ。
まだ、生きていると思うけれど、どうしているのかな……。
どんな20代だったのですか?
在学中から時事通信社でバイトして、卒業後は角川書店の『バラエティ』に半年いてから辞めて、在学中から手伝いで呼ばれていた講談社の『PENTHOUSE』にフリー記者として24歳から28歳まで在籍、休刊後に『Hot-Dog PRESS』の契約編集者を3年半やって、32歳で辞めてフリーになりました。
だから、20代は雑誌の仕事をがむしゃらにやっていた時代ですね。
特に、『PENTHOUSE』では70ページくらい担当したこともありました。
200ページくらいの雑誌なのに。
そのときのギャラはすごかったですよ。
だから、生まれて初めてメニューの金額を見ないで頼んだのはこの頃です。
忙しかったからお金を使う暇もなかったこともあって、いまよりぜんぜん余裕があった(笑)。
月収2万円から始めて、4年たったら月に5~60万円はもらっていました。
フリーになった30代、社員を抱えてつらかった40代
32歳でフリーになられていますね。
雑誌の仕事は好きなんだけど、ものすごく忙しいし、自分が消費していくのがわかるんで、辞めました。
その頃、ワニブックスで書籍の編集をしていた知人と飲んでいたら「書籍の仕事も面白いですよ」と言われて。
確かに、書籍は雑誌と違ってちゃんと残るものだし、ひとりで全部に携われるので、映画監督みたいなものなんですよ。
『なるほど、書籍という手もあるな』と思いました。
そのころ、坂崎靖司さんという人の本『編集バカとバカ編集者』を読みました。
その本にフリーで書籍編集をやることについて書いてあり、その影響も大きかったですね。
余談ですけど、『書籍やりたいなあ~』と思ったころに、秋元良平さんのごく薄い写真集『盲導犬になったクイール』を書店で見て、たまたま買ったんです。
そしたら、盲導犬には3人の母親がいると書いてあって、それにすごく心打たれた。
実は僕にも3人の母親がいるんですよ。
『僕と一緒だ』と思いました。
それがすごく心に残っていましたね。
でも、まさかその後、『盲導犬クイールの一生』を作ることになるとは思っていなかったです。

それで、フリーになって書籍の仕事を始めるわけですね。
ひとりで事務所を借りるお金はなかったから、デザイン事務所をやっていた友達に頼んで、月3万円で机を置かせてもらいました。
毎日、その事務所に行って、打ち合わせは喫茶店でして、みたいなことを3年やっていました。
このままひとりでやっていてもいいとは思ったんですけど、そのうち有限会社を作ることにして、1997年に書籍のプロデュースオフィス「ブルー・オレンジ・スタジアム」を設立しました。
起業するという意識はあまりなくて、ないのとあるのとではあったほうがいいよね、というくらいの軽い気持ちでした。
まあ、スタッフ分や、まとまった入金&支払いの面でも、個人より会社にしたほうが会計的にラクというのもあったんですけどね。
すると会社に入りたいという若手が現れはじめて、最大、4人まで増えました。
36歳のころに有限会社を作って、いかがでしたか?
最初は宇田川町の狭いワンルームマンション。
でも、5年後には渋谷の松濤にけっこうでかいオシャレな事務所を借りました。
でも、社員に給料を払わないといけないから、僕がやりたくない仕事もやらなくてはいけない。
4人いると楽しいんですけど、それも疲れてきちゃって。
僕は完璧主義者だから、完全に任せるということができないんですよ。
そうすると自分の仕事がどんどん増えていくんです。
それなりに作った書籍の点数は残しているし、ほどほどの満足感はあるけれど、ちょっとすり減っていた感じでしたね。
ブルー・オレンジ・スタジアムというのは編集プロダクションだったんですか?
編集プロダクションではないのですよ。
プロデュースオフィスと言っていました。
なぜかというと請負仕事はしないから。
「取ってくる」みたいなのは絶対にしない。
僕やスタッフが考えて企画を出して版元を決めていくという、プロデュース。
企画から編集まで全部、自分たちでやる。帯まで全部決める。
基本的に決定権は僕にあると思ってやっているからです。
仕事のスタイルを確立した50代
いまはおひとりで仕事をされているわけですね。
社員をクビにするのは嫌だから、辞めても新人を入れないようにしました。
それで、最後、社員がゼロになった段階で事務所は引き払って、51歳のときに自宅で仕事をするようにしました。
いまは作業で体力はすり減っているけれど、精神的にはすり減っていないですね。
ものすごいスケジュールで頑張っているけど、会計的には僕のことだけ考えていればいいので、すごくラクです。
編集の仕事をされなくとも、著者だけでやっていっても十分なんじゃないですか?
僕は編集の仕事が好きなんですよ。
一度、「編集者辞める」って宣言したんだけど、いつの間にかまた、プロデュース・編集の仕事が増えて、いま、100冊近くのネタを抱えてます。
僕が生きている間に100冊は作れない。すでにげんなりしていますよ(笑)。
だから、自分の著書はついつい後回しになる。
僕の頭の中ではできちゃっているから面白くないんですよ(笑)。
でも、プロデュース・編集の仕事は、僕の頭の中には完成していないものだから。そう言いつつ、ネタを仕込む段階で大枠は頭のなかではできているんですけど。
そこから、著者やデザイナーとやり取りするなかで、カチッと固まっていく。
そういうのが好きですね。じわじわと物体化していくのが快感なんです。

若者へのメッセージ
若い人へのメッセージってありますか?
僕は「宣伝会議」の、「編集・ライター養成講座」で講演していて、そこの受講生に言うのは、「人と同じことはダサイとまずは思ってほしい。人と同じでは食えなくなる」ということ。
つまり、オリジナリティが大切、ということです。
オリジナリティって自分が発するものだと思っているようだけど、趣味や嗜好で十分、オリジナリティは発揮できます。
僕はみんなが見ているものは見ないと心がけています。
ベストセラーは読まないし、大ヒット上映中といわれた瞬間、見たいと思わなくなる(笑)。
それは、人とは違うことを見るクセをつけるため。人と同じことをやっていたら、いつかどんどん有能な人が出てきてしんどくなる。
だから、自分らしいオリジナリティを持つべきだと思います。
なぜ、人と同じことをするんでしょうね?
目立つのが怖いんじゃないでしょうか。
ネットのせいだとは思いたくないけれど、人と違うことが恥ずかしいと思ってるのかもしれない。
なんだか逃げ腰になっている感じがしますね。
石黒さんにとって“粋”とは?
匠の技とか、誰にも気づかれないような渋い作業は好きで、なんです。そういうのが粋だと思います。
僕は日ごろから「粋だ」「粋じゃない」というのはよく言っているんですよ。
役に立つことはいいことだけど、そこばかり見ていたら、粋じゃない。
役に立たないことに粋は潜んでいると思っています。
あと、さっき言った、「みんなと同じことを考る」ことも粋じゃない。
みんなと同じことを考えたって、右から左にどんどん流されていくだけだから。
いかに人とは違うことを考えられるか?人と同じことは粋じゃないから辞めたほうがいいと考えます。

1961年、石川県金沢市の生まれ。著述家・編集者・分類王
星稜高等学校卒業後、東京芸大油画科を目指して上京。御茶の水美術学院に入り3浪して断念、日本ジャーナリスト専門学校に入学。
在学中から時事通信社運動部でアルバイを。
卒業後、角川書店『バラエティ』で編集者見習いで入るが半年で辞め、在学中から関わっていた講談社『PENTHOUSE』のフリー記者・編集者に。休刊により同社『Hot-Dog PRESS』の契約編集者に。
3年半在籍したのち、1993年にフリーに。
1997年に書籍のプロデュースオフィス「有限会社ブルー・オレンジ・スタジアム」設立。
『餃子の創り方』『ザ・マン盆栽』などパラダイス山元の本、『ナガオカケンメイの考え』ほかナガオカケンメイの本、ベストセラー『ジワジワ来る○○』(片岡K)、犬山紙子『負け美女』、『ネコの吸い方』(坂本美雨)、『人が集まる「つなぎ場」のつくり方』(ナカムラクニオ)、『凄い!ジオラマ』(情景師アラーキー)など230冊をプロデュース・編集する。
著書には、映画化されたベストセラー『盲導犬クイールの一生』、糸井重里氏に高評価を得た『2択思考』、図表を駆使し森羅万象を構造オチの笑いとしてチャート化する“分類王”の『図解でユカイ』ほか、『エア新書』『ダジャレ ヌーヴォー』『カジュアル心理学』『短編集 犬がいたから』『CQ判定 常識力テスト』『ベルギービール大全』『ナベツネだもの』など幅広いジャンルで多数。近刊著書は、『分類脳で地アタマが良くなる』(KADOKAWA)。
また、「全国キャンディーズ連盟」代表、「日本ビアジャーナリスト協会」副会長でもある。



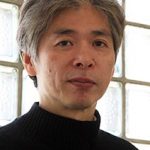 大橋博之
大橋博之













































 IKITOKI(イキトキ)とは
IKITOKI(イキトキ)とは